はじめに
今、私たちがポケットに入れているスマートフォンは、ほんの100〜150年の間に劇的な進化を遂げてきました。本記事では、技術の変遷と社会との関わりに焦点を当てながら、シニアも知りたい電話の歴史を時代ごとに振り返ります。

1. 明治期:電話技術の導入と試行(1870〜1900年代)
電話の誕生と日本への導入

- 電話は1876年、アレクサンダー・グラハム・ベルによって発明されました。
- 日本には1877年(明治10年)にベルの電話機2台が輸入され、工部省と宮内省での実験通話が行われました。
- 当初はあくまで実験的・限定的な使われ方で、官庁や重要機関でのみ導入が進みました。
一般への普及の始まり
- 日本で本格的に電話業務が始まったのは、1890年(明治23年)。東京‐横浜間での電話サービス開始がその契機となりました。
- 最初の加入世帯数は非常に少なく、東京と横浜合わせてわずか197世帯程度。
- 電話機器や回線設備の制限、そして高額なコストなどから、普及速度はゆるやかでした。
交換手と手動接続の時代

- 明治期の電話では、発信者が直接相手につなぐ仕組みはなく、「交換手」と呼ばれる人が、手動で回線をつなぐ方式が取られていました。
- 発信者は受話器をあげ、交換手を呼び、つなぎたい相手の名前を口頭で伝えて交換手が線をつなぐ…という方式です。
公衆電話の登場
- 一般向け電話がまだ普及していない時代、公共の利用を意図して駅構内などに公衆電話が設置され始めました。最初のものは1900年(明治33年)に、上野・新橋駅構内に設置された「自動公衆電話」です。
- この「自働電話(自動公衆電話)」は硬貨投入型でしたが、5銭、10銭が入ったかどうかをベルの音で判断して交換手が判定するという仕組みを使っていた、という記録もあります。
2. 大正・昭和前期:交換機の自動化と普及拡大(1910〜1940年代)
自動交換機の導入

- 加入者数が増えるにつれて、交換手による手動接続は限界を迎えます。そこで「自動交換機」が徐々に導入され、発信者がダイヤルを回して番号を入力する方式に転換されます。
- 日本では1920年代から自動交換機が導入され、段階的に拡大していきました。
家庭への普及と加入数の拡大
- 戦前までには、電話加入数・機器数ともに伸びていきましたが、まだ一般家庭への普及率は低く、一部の上流階級や企業・官庁に限られていました。
- 1937年(昭和12年)時点で日本国内の電話加入数は約98万人、電話機119万台、人口千人あたり17台程度という水準でした。
公衆電話の拡充

- 通信インフラが整備されるに伴って、公衆電話の数も増加。街角電話や駅、公園など公共空間にボックス型の電話が設置されるようになりました。
- 昭和期には、黒電話スタイルの固定電話機が一般的となりました(いわゆる「黒電話」)。
3. 戦後〜高度経済成長期:電話網の整備と通信革命(1950〜1980年代)
戦後復興と固定電話の伸び
- 第二次世界大戦後、日本は復興を経ながらインフラ整備が急速に進み、固定電話網も全国に拡大していきます。
- 1952年、電電公社(日本電信電話公社)が発足し、電話事業が一体的に管理・運営されるようになりました。
市外通話の自動化
- 市内通話は比較的早期に自動交換方式となりましたが、市外通話(遠距離通話)はしばらく交換手による接続が残っていました。
- 県庁所在地級の都市で市外通話が自動化されたのは1967年、全国一般に拡大したのは1978年との記録もあります。
参考資料~https://kantuko.com/ncolumns/
公衆電話の隆盛とテレホンカード
- 公衆電話は日常生活の一部になり、多くの人が利用するようになりました。
- 1982年にはテレホンカードが導入され、コイン式からカード式へと移行が進み、利便性が上がりました。
- 公衆電話は、待ち合わせ、緊急通話、恋人同士の連絡場所などとして、文化的にも象徴性を帯びるようになります。
4. 携帯電話・モバイル時代の幕開け(1980〜2000年代)
携帯電話の登場

- 日本で最初の携帯電話サービス(自動車電話など含むモバイル電話形態)は、1985年(昭和60年)ごろから始まりました。
- これら初期の携帯電話は非常に大型で、高額、そして機能は通話のみという制限されたものが多かったです。
ケータイ文化の台頭
- 1990年代以降、日本では「ガラケー(ガラパゴス携帯電話)」と呼ばれる独自進化を遂げた携帯電話文化が発展しました。
- 電話・メール・ウェブ閲覧・写メールなど、多機能化が進み、若者を中心に携帯が生活の中心となっていきます。
技術世代の移り変わり

- 2G → 3G → 4G と、通信速度やデータ通信の性能も向上していきました。
- 日本の通信会社、特に NTTドコモ は、PDC(2G方式)、FOMA(3G方式)、Xi(4G方式)といった方式を順次展開。ウィキペディア
- また、PHS(Personal Handy-phone System)というローカル・無線電話方式が普及した時期もあります。ウィキペディア
5. スマートフォン・現代(2000年代後半〜現在)

スマートフォンの普及
- iPhone の登場を皮切りに、スマートフォン(通話+高機能コンピュータ)が急速に普及しました。
- 従来の携帯電話の役割を引き継ぎつつ、インターネット、SNS、動画、決済、カメラなど多機能を融合した端末として多くの人々の生活必需品になりました。
固定電話からスマホへ流動
- 固定電話加入数は近年減少傾向にあり、スマホ中心の通信スタイルが定着しています。
- かつて全国にあった電話帳(ハローページなど)も、その発行部数は激減しました。
次世代通信:5G へ
- 現在、多くの国・地域で 5G 通信が普及し始めており、将来は 6G、IoT(モノのインターネット)、さらには衛星通信なども組み合わさった通信環境が一般化していく見込みです。
まとめ:電話の役割と未来展望
電話は、もともとは限られた人々のための通信手段として始まりました。
そこから技術革新とともに、交換機、自動接続、モバイル化、スマート化へと進化を遂げ、今では誰もが持つ、なくてはならない存在になっています。
未来においても、通信速度の進化、より広域で安定したネットワーク、さらにはAI連携や拡張現実(AR)/仮想現実(VR)との融合など、新たな局面を迎えるでしょう。

タンソク
未来のスマホは楽しみです、まだまだ元気で確かめたい!
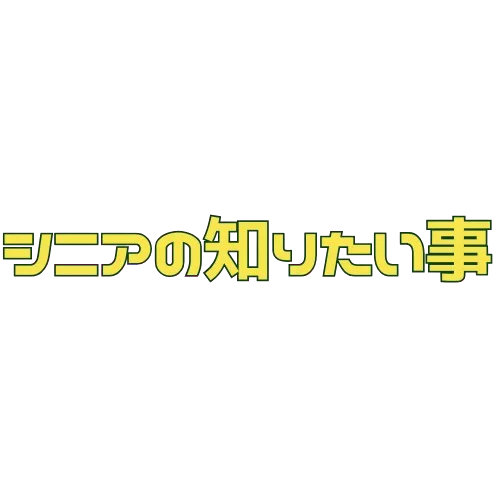



コメント